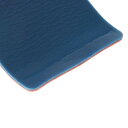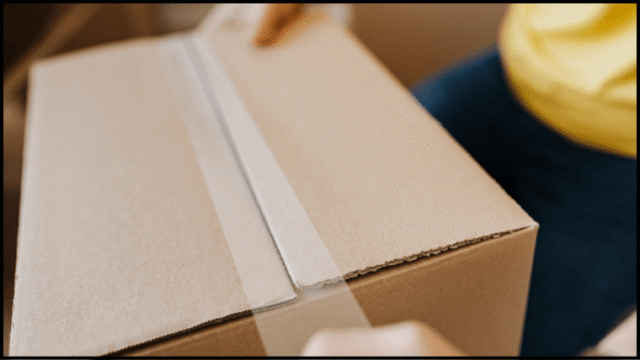過去の経験活かして登山用の救急セット準備したら、とんでもないサイズになったんだが?

こんにちは、マツです。
私は登山したいなぁ!って春先に思い立ってあれから約半年以上、準備だけを着々と進めて一歩たりとも山に行っていない丘サーファーならぬ自宅登山部幽霊部員状態のものです。
実際に登山部があれば幽霊部員クラスだと思うので、中学時代のバドミントン部の幽霊部員以来で懐かしい気分になります。
そんな昔話はさておいて、今回登山用の命と体を守る救急セットを準備しようということで、まだ仮置きではあるものの、ある程度救急セットアイテムが揃ってきたのでパッキングしてみました。
仮パッキングの結果としては、そもそもサイズ感からとんでもないサイズに巨大化しており本当にこんなんで登山道具パッキングできるの?というUL(ウルトラライト)化に警鐘が鳴らされています。
前置きはこれくらいにして本題に入っていきましょう。
過去の経験を活かすと必須アイテムのボリュームが跳ね上がる
そもそもの話、私マツは元々スキー場のパトロール隊員の一員でした。でしたという前置きを書いたのは、今年からはパトロール隊員として活動しないことを自分の中で決めているからです。
そこまで大した経歴でもないですが、いちをパトロール隊員暦は3年目でパトロール界では新参者の初心者ペーペーにラインナップされるポジションです。そんな私の経験ではありますが、いちを日々遭遇する怪我人との対応でいちをどのようなものが必要になるのか、処置はどうするのか?みたいな現場を見てきた経験を活かして今回救急セットを準備しました。
備え始めればキリがない救急セットですが、スキー場の現場でよく遭遇していた怪我と必要になる救助アイテムを総括すると、私が想定しているソロ登山でひとまず備えるべきは骨折対応だと考えました。
重症なものであれば、首の骨の骨折や背骨の骨折などの備えもパトロール隊の時準備していました。ですが、正直ソロ登山でそこまでの事態に陥ったら、結局一人でどうこう対処できる状態ではありません。
ひとまず骨折対応で真っ先に考えたのが三角巾を準備することです。
いちを三角巾があることで、ひとまず患部の固定を行うことができます。またたとえば腕の骨折なんかでも首から吊り下げることもできたり、縛ることで患部の圧迫もできるようになります。
こんな感じで三角巾を準備することで様々な対処ができることになります。
パトロール隊の時には救急セット1組に三角巾は5組準備していましたが、私の場合には怪我の箇所を1箇所と仮定して3組準備することにしました。いちを3組準備しておけば最悪足を骨折しても固定できるのでなんとかなるかなという想定です。
そもそもYouTubeなどで情報発信している人の中に三角巾なんか持ってる人を見たことがありません。大体あるのが怪我の予防のテーピングだったり、具合が悪い時の飲み薬、擦り傷が出た時の塗り薬だったり絆創膏なんかが主だったもののように見えました。
もちろん怪我をしに山に入るつもりはないので、そこまでの大型な装備は必要ないでしょう。というのが準備している人たちの考えでしょうが、スキー場の来場者も怪我をするつもりはありませんが、怪我をしてパトロール隊のお世話によくなるし、救急車の出動もしょっちゅうでした。
YouTubeなどでも稀にヤバい量の救急セットを持っている方を見つけることがありますが、こういった人はまさに現場経験がある人なんだろうなと私自身は思うことが多いです。なんていっても簡単に考えると、人間が体験する怪我とが体調不良とかって、いいところ擦り傷・切り傷と体調不良くらいですもんね。
仮の救急セットの重量を量ったら300gを軽く超えてた
私の仮の救急セットの重量を量ったら340gくらいを軽く超えていました。現状私が今準備不足になっているのが次の内容です。
- 飲み薬
- 塗り薬
- 骨折時の固定用アイテム
こんなところでしょうか。最悪腕や足を骨折した時にはポールを分割してでも固定する気満々ではあるんですが、骨折対応用の専用のアイテムがある方がいいですよね。なんといっても骨折した時には支えが欲しいですから、貴重なポールが減るのは一大事ですからね。
その他、普通の登山者の方が常備しているであろう飲み薬や塗り薬もまだ準備していません。自宅にはある程度の常備薬も準備してますが、登山用で必要になるものもいくつか改めて買い集める必要もあったりします。
始めのうちは救急セット用に防水スタッフサックも準備しようと考えたんですが、スタッフサックいくつか持っていて、実際に使っているからわかるんですがスタッフサックは視認性が非常に悪いんですよね。
スタッフサックは防水対策とかコンプレッション性能(圧縮性能)としては有能だと思いますが、物の取り出しに関しては正直使い勝手が悪いと考えています。
いろいろな発信者の情報を参考にしながら一番簡単に手に入りやすく、なおかつ視認性も高く、さらにはダメになっても悲しくないアイテムのジップロックを採用することにしました。
現在使用しているジップロックはLサイズを使用しており、内容量的には6〜7割が埋まっているという感じでしょうか。この状態で塗り薬、飲み薬は大した量じゃないにしても骨折固定用のアイテムを入れるとほぼ内容量がパンパンになるのではないかと思います。
怪我の備えでひとまず重要になるのが患部の洗浄
ひとまず怪我の発生で一番多いと考えられるのが、擦り傷だったり切り傷ではないかと思います。怪我の発生箇所などによっては、傷口から感染症を発生する可能性もあると思うので、ひとまず初期対応として重要になるのが患部の洗浄だと思います。
患部の処置に関しては専門の方の方が詳しいとは思いますが、今時は消毒液とかは使いません。昔だと傷口もガーゼとか絆創膏を貼って放置って感じでしたが、今は全然対応が違うんですよね。
ひとまず患部の洗浄をするとなると必要になるのが水です。
登山している方であればひとまずある程度の水は常備していると思うので、患部の洗浄はできると思います。ただ登山中の水は、飲み水としても重要なポジションになるので、むやみやたらにガバガバと患部を洗浄できるというわけではないわけです。
最低限の水の量で患部を洗浄できるように準備するのが、私の場合にはペットボトルのキャップです。もちろんペットボトルのような形状のボトルを持ち歩いていない場合には活躍の機会はありませんが、大半ペットボトルを持っていることも多いでしょう。
そんなペットボトルのキャップに小さい穴を開けて、キャップだけを救急キットに忍ばせておきます。いちをキャップを準備した段階で水の出方のテストはしておいた方が無難です。思っている以上に水の出が悪かったりとか、逆に水が出過ぎて大変だったとか色々トラブルの種があるでしょうからね。
すごい細かいところですが、私自身が気になって、あとから自分で加工した部分があります。それがペットボトルのキャップのバリ取りです。
キャップにバリ?!って思うかもしれませんが、キャップ単体で持ち歩くことを考えると、キャップの口が案外ギザギザとバリが出ていて結構危ない形状です。いちを救急キットの中に忍ばせているアイテムにもなるので、他のアイテムを傷だらけにしないためにも、事前にキャップのバリはやすりで削り落としておきました。
ペットボトルで水を持ち運ばなくても、ウォーターバックなどのキャリーケースは大体ペットボトルの口と同じ形状に作られていることが大半なので、ペットボトルで水を持ち運ばなくてもウォーターバックを使って洗浄することもできると思います。
患部の洗浄後は止血もしくは圧迫
患部洗浄後の止血だったり圧迫を考える時は、だいたい擦り傷とか切り傷で使うことが多いと思いますが、いちを次の対応も頭に置いておくと無難ですよね。
止血や圧迫を行う時には、滅菌処理されたガーゼがあるといいですよね。いちを傷口の処理などをする前には、感染症などの対策としてゴム手袋なんかも着用しておいた方がいいので、ゴム手袋も救急セットに何セットか常備しておく方がいいです。(最低でも使うものと予備の2セットくらいは準備したいものです)
案外使い勝手が悪いのが絆創膏だったりします。処置が必要な怪我となると、大体小型のガーゼだったり中型のガーゼで傷口付近の清掃とかを行うことも多く、あまり絆創膏貼ってOK!とはならないのが現場での出来事です。
救急セットを使う時となると、大体患部を水やガーゼなどで洗浄・清掃、その後ガーゼで圧迫・止血という流れになることが大半で、あまり普通の人が想定するような絆創膏貼ってOKだね!ってケースはほぼない感じがします。
最近では絆創膏も中型のものとか大型のものもあったりするので、その辺も持ち運ぶと便利だとは思いますが、現場経験的にはそこまで使用頻度が少ないアイテムだなと思います。

結構厄介なのが血液サラサラの薬を飲んでいる方の場合
あまりこういった話を耳にすることが少ないですが、現場でたまにあるのが止血しても血が止まらないというケースです。
怪我した人に話を伺うと、大半が血液サラサラの薬を飲んでいて、血が止まりにくいのよ。ってことでした。
正直止血が済めば初期対応としてはOK!みたいな雰囲気がありますが、止血が終わらないことで、何度も傷口付近の清掃を行ったり、圧迫用のガーゼを何度も交換したりと、この血液サラサラによる影響は結構大変だなと思うことが多いです。

擦り傷と切り傷だと、その後は圧迫固定して終わりかな
普通の人が一番想像しそうな怪我の第1位と第2位が、きっと擦り傷と切り傷だと思う。その2つに関しては、患部の洗浄と傷口の止血と保護ができればいいと思うので、怪我した直後であれば、あとは止血するために圧迫して固定すればOKだと思います。
最近だと傷口の乾燥を防ぐようにハイドロコロイド?とかいうガーゼなしの絆創膏みたいなものもあるみたいで、そちらを貼る方が治りが早いというのが一般的なんだとか。
個人的には冬のスキーシーズンになれば、古傷のアキレス腱断裂の傷の箇所が毎日スキーブーツとの靴擦れで生傷全開の私として、ハイドロだろうがガーゼだろうが治るのは時間がかかるというふうに思っている。
なんといっても、どちらで対応しても正直靴擦れみたいな状況から逃げ出せないような場合の傷であれば、常に毎日生傷になる状況だったりします。また、完全にスキーブーツから離れてもうスキー乗らんって時には、勝手にというか気付かぬうちに自然治癒しているしということで、あまり傷口の治りの速さを気にすることがないというが私の体験上の話です。
もちろん正確にデータを取りさえすれば、どちらがどれくらいの日数とか時間早く治るのか確認することができると思うが、そんな研究者みたいな一般人がどれくらいいるのかは完全に疑問だ。
最後に
私のソロ登山用の救急セットの準備はまだ道半ばという感じで、正直完全版の完成には程遠いような気がする。そうはいっても救急セット(仮)ができもしなければ登山にも行けないしということで、なんとか投薬類と塗り薬セットを準備して、救急セット(仮)を準備しなければ。
もちろん何もないのが一番だし、使わないに越したことがない。
あまりに使わなければUL(ウルトラライト)に少し方針転換することもあるかもしれないけども、自分以外でも怪我人に会うこともあるかもしれないし、何事も備えるに越したことがないと思うわけである。
登山経験がない自分が何かと準備していきながら気になっていることは、事前に準備したバックパックの容量が、もしかしてかなり小さすぎるのではないか?ということが救急セットを準備して気になってきた。そうはいっても、すべてのサイズが大きいというわけでもないだろうし、いろいろ準備しているアイテムもULを意識して軽量のものを探してるのもあるので、きっとなんとかなんだろう!
人生進んでみれば案外なんとでもなるものだ!ということで、今回の記事はこれくらいにして終わりにしようと思う。
少し長くなってしまいましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。